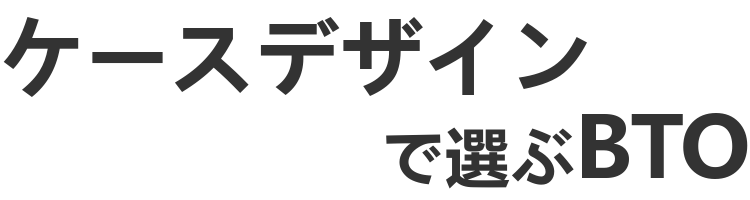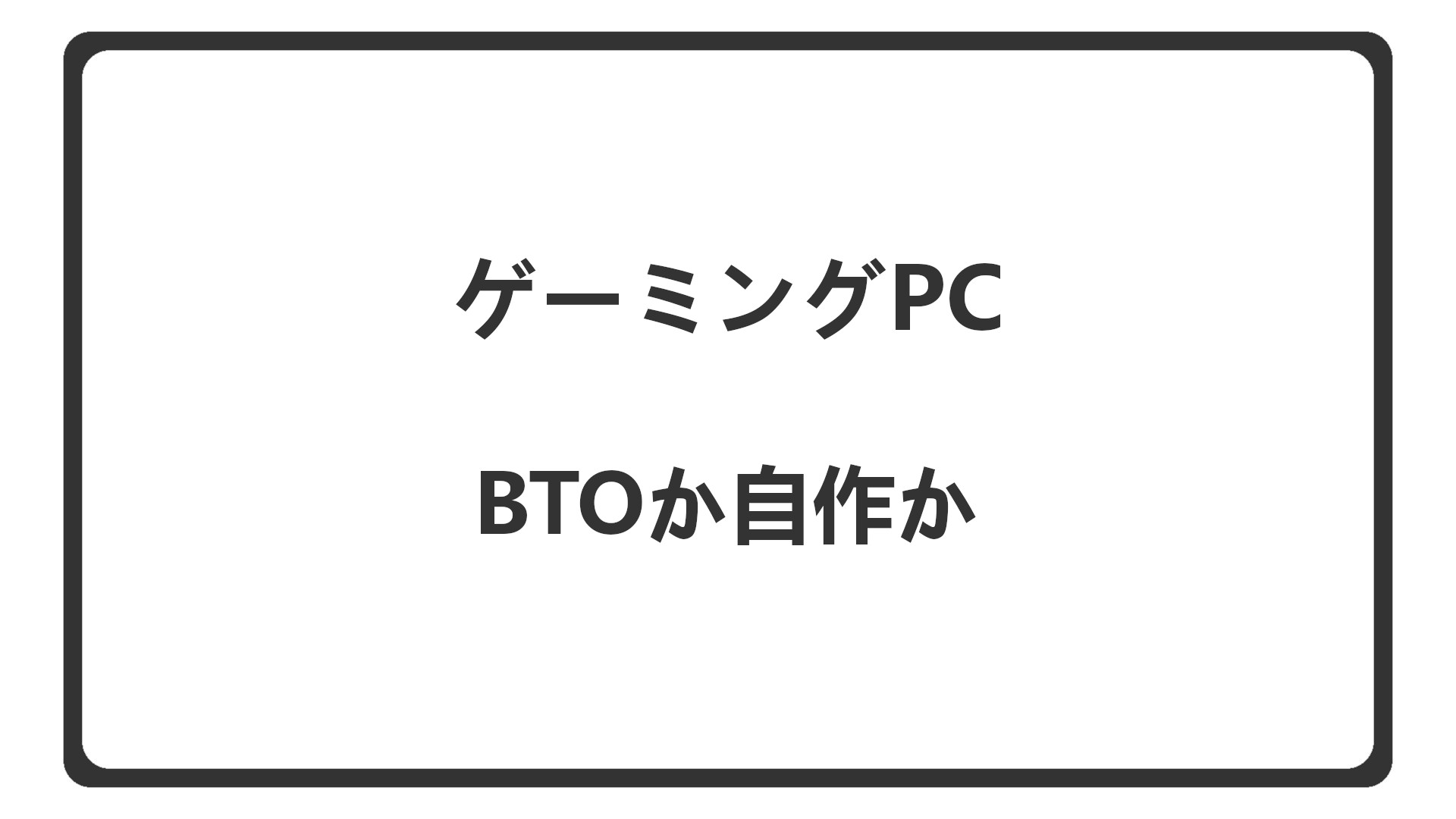「新しいPCが欲しいけど、種類が多くてどれを選べば良いかわからない」
「BTOパソコンと自作パソコンって聞くけど、何が違うの?初心者にはどっちがおすすめ?」
初めてのゲーミングPC選びは、期待でワクワクする反面、専門用語が多くて戸惑うことも多い。特に「BTO」と「自作」は、どちらが良いか悩むポイントだ。
結論から言うと、PC初心者には断然「BTO」をおすすめする。
この記事では、なぜPC初心者にBTOが最適なのかを、自作との違いや、それぞれのメリット・デメリットを交えながら、わかりやすく解説していく。
BTOパソコン、自作パソコンとはそもそも何?
- BTOパソコン:BTOが提示した選択肢から自分でパーツを選び、BTOが組み立てて完成させるPC
- 自作パソコン:自分で選んだパーツを自分で組み立てて完成させるPC
それぞれの特徴を簡単に見ていこう。
BTOパソコンとは?
BTO(Build To Order)は「受注生産」という意味で、注文を受けてからパソコンを組み立ててくれるサービス・ショップのことだ。
BTOが用意したモデルをベースとして、そこからメモリやストレージなどのパーツを、用意された選択肢の中から自分好みにカスタマイズして注文できる。BTOによってカスタマイズできるパーツや選択肢の多さが異なる。
注文後、BTOが組み立てや動作確認まで行い、完成品を届けてくれる。
有名どころのBTOで言えば、ドスパラ、マウスコンピューター、フロンティアなどがある。
自作パソコンとは?
PCを構成する全パーツをすべて自分で選び、自分で組み立てや動作確認まで行うPCが自作パソコンだ。
完全にゼロの状態から自分の好きなパーツでPCを組むことができるため、性能・デザイン・光らせ方まで、本当の意味で自分好みの構成に仕上げられる。
ただしパーツには規格や相性があり、すべてのパーツを好き勝手に組み合わせられるわけではない。相性が悪いパーツを選んでしまうと、物理的に組み合わせられず完全に無駄になってしまったり、発火したりすることもあるというデメリットを覚えておこう。
PC初心者にはBTOをおすすめする6つの理由
自作パソコンにも魅力はあるが、特にPCを初めて購入する人や、PCの知識に自信がない人は、BTOを選ぶメリットが非常に大きい。
BTOをおすすめする主な6つの理由は以下の通り。
- 圧倒的に手軽!届いたらすぐに使える
- 保証とサポートが充実していて安心感が違う
- パーツ選びで失敗する心配がない
- チューニング不要
- 結果的に安くなる場合もある
- 目的に合ったバランスの良い構成を選びやすい
圧倒的に手軽!届いたらすぐに使える
BTOの最大のメリットは、手軽さだ。
- 組み立て不要:面倒な組み立て作業が一切ない。
- OSインストール済み:Windowsがインストールされた状態で届くため、難しい初期設定に悩む必要がない。(OSなしモデルも一部ある)
- 動作確認済み:BTOが動作確認を行ってから出荷してくれるので安心。(初期不良が起きる可能性はある)
ゲーミングPCが届いたら電源ケーブルやモニターなどをつなぎ、簡単な初期設定を済ませるだけですぐに使い始められる。
「PCは欲しいけど難しいことは苦手」「忙しくて組み立てる時間がない」という人にはBTOが最適だ。
保証とサポートが充実していて安心感が違う
PCは精密機械なので、万が一の故障はつきものだ。しかしBTOであれば、安心感が違う。
- PC全体の保証:BTOはパソコン全体に対して保証を提供している(通常は1年保証。延長オプションもある)。どこか1つのパーツが故障しても、BTOに修理を依頼するだけで良い。
- 充実したサポート体制:電話やメールでの問い合わせ窓口が用意されていて、困ったときに相談できる。BTOによっては、チャットサポートや訪問サポートを提供していることもある。
自作パソコンの場合、保証はパーツごとに分かれている。PCが故障した場合、どのパーツが原因なのかを自分で特定し、故障したパーツのメーカーに個別で連絡して、修理や交換の手続きをし、自分で取り換える必要がある。
そもそも本当にそのパーツが壊れているのかの断定も難しく、初心者にはハードルが高い作業だ。
パーツ選びで失敗する心配がない
BTOであれば、パーツ選びにおける失敗がない。
- 動作確認済みの組み合わせ:BTOが提供するカスタマイズの選択肢は、基本的に動作確認が取れたパーツの組み合わせとなっている。
- 相性問題の心配不要:「このパーツとこのパーツは使えるかな?」「このクーラーで冷却力は足りるかな?」と悩む必要がない。
PCには、CPUとマザーボードの規格が合わない、メモリが対応していない、ケースにグラフィックボードが入らない、CPUクーラーの冷却力が弱くてCPUを冷やせない、などの相性があり、知識がないと組み合わせを間違えてしまう可能性がある。
自作パソコンの場合、PCパーツの規格について知識を付け、パーツごとの詳しい性能まで知ったうえでパーツを選ぶ必要があるが、BTOであれば学びの手間や失敗の可能性がほぼない。
チューニング不要
BTOパソコンは、PC全体で性能をチューニングしてくれていて、十分な性能を発揮しながらも、それなりの冷却力で事足りるという、バランスが非常に優れている。
例えばPC全体の冷却能力に合わせてCPUの出力を調節したり、搭載できるグラフィックボードを決めたりしてくれている。
一方で自作の場合は、パーツの組み合わせの検証データがないため、試行錯誤しながら最適な性能と冷却力のバランスを試す必要があることもある。
結果的に安くなる場合もある
BTOパソコンの価格には「工賃」や「BTOの利益」が含まれるため、基本的には自作パソコンより価格が高くなる。
しかしBTOパソコンのほうが結果的に安くなる場合もある。
- メーカーの大量仕入れ:大手BTOはパーツを大量に仕入れるため、個人でパーツを1つ1つ購入するよりも安く調達できる場合がある。
- キャンペーンやセール:BTOは定期的にキャンペーンやセールを実施していて、お得に購入できるチャンスがある。
- 自作の失敗:自作の組み立て最中に、パーツを破損させたり、相性問題が起きたりすると、買い直す必要がある。「ピン折れ」など、初心者がやってしまいがちな失敗もあり、破損は珍しい話ではない。
目的に合ったバランスの良い構成を選びやすい
主にCPUとグラフィックボードにおいて、BTOではバランスの良い組み合わせになっていることが多い。
例えばCore i9-14900K×RTX4060のような、ハイエンド×エントリーのアンバランスな組み合わせのモデルは少ない。
現実的に、RTX4060を選ぶような人は、Core i9-14900KほどのCPUを必要としないことが多いのだ。
余計な選択肢がなく、バランスの良い構成で固められているのもBTOのメリットだ。
BTOパソコンの注意点やデメリット
BTOパソコンにはいくつかの注意点やデメリットがある。
- カスタマイズの限界:BTOが用意したパーツ以外は選べない。特定のメーカーのパーツを使いたい、デザインに徹底的にこだわりたい、という希望は叶えにくい。
- パーツ詳細が不明な場合も:電源ユニットやメモリなど、一部のパーツでメーカー名や型番名が記載されていないことがある。信頼できるBTOであれば、一定の品質基準を満たしたパーツを使用しているとはいえ、気になる人は気になる。
- 自作ほどの拡張性はない:ケースやマザーボードによっては、将来的にパーツを増設・交換するのが難しい場合がある。
とはいえこれらのデメリットは、多くの初心者の人にとっては大きな問題にならないことが多い。まずはBTOで安心して使えるPCを手に入れることが重要だ。
ちなみに:自作パソコンが向いているのはこんな人
BTOをおすすめしてきたが、自作が向いている人もいる。
- パーツ選びから組み立てまでのプロセスそのものを楽しみたい人
- PCの内部構造や仕組みを深く理解したい人
- 性能やデザイン、光り方など、細部まで徹底的にこだわりたい人
- トラブルが発生しても、自分で原因を突き止め、解決する意欲や知識がある人
- 将来的に自分でパーツを交換・アップグレードしていくことを見据えている人
PCを自作する人の中には、「パーツを選んでいるときが一番楽しい」という人もいるほどだ。
ちなみに、半自作のように広い選択肢からパーツを選んでゲーミングPCを組めるBTOもある。カスタマイズ幅が売りのBTOはいくつかあるが、おすすめはSEVENだ。
›【ケース一覧付き】SEVENの評判は?メリット・デメリットを徹底解説
まとめ:PC初心者にはBTOが安心で確実
この記事では、BTOと自作の違い、なぜPC初心者にはBTOがおすすめなのかを解説した。
- 手軽:組み立て不要ですぐに使える
- 安心:保証・サポートが充実
- 確実:パーツ選びで失敗しない
- 楽:チューニングが不要
- お得:結果的に安くなる場合も
- 簡単:バランスの良いモデルを選びやすい
もちろんBTOにもデメリットはあるが、それを補って余りあるメリットがある。
初心者はまずはBTOパソコンで快適なPCライフをスタートさせ、PCに慣れ親しんでいこう。将来的に「もっとこだわりたい」「自分で作ってみたい」という気持ちが芽生えたときに自作パソコンに挑戦してみる、というステップがおすすめだ。
この記事を参考に、自分にピッタリのBTOパソコンを見つけよう。
›【これで完璧】初心者でも失敗しないBTOゲーミングPCの選び方を徹底解説